補助金と助成金の違いとは?給付金との比較と選び方

「事業を成長させたいけれど、資金が…」「新しい設備を導入したいけど、費用がネック…」
中小企業の経営者や個人事業主の皆様、そして企業の経理・総務担当者の皆様、このようなお悩みはありませんか?国や自治体は、事業者の様々な取り組みを支援するために、「補助金」や「助成金」といった制度を用意しています。
しかし、「補助金と助成金って、何が違うの?」「どちらが自社に合っているの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、補助金と助成金の基本的な違いから、それぞれの目的、種類、メリット・デメリット、さらには「給付金」との違いまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
この記事を読めば、自社に最適な支援制度を見つけるための第一歩を踏み出せるはずです。
補助金と助成金4つの主な違い
補助金と助成金は、どちらも国や地方公共団体から支給される返済不要(原則)の資金ですが、いくつかの重要な違いがあります。まずは、代表的な4つの違いを押さえましょう。
財源の違い
【補助金の財源】
主に税金(法人税等)です。そのため、国の政策目標(例:中小企業の生産性向上、地域経済の活性化、イノベーション創出など)を達成するための事業が対象となることが多いです。
【助成金の財源】
主に雇用保険料(労働保険料の一部)です。そのため、雇用の安定、労働環境の改善、従業員の能力開発など、労働に関連する取り組みが対象となることが多いです。
管轄省庁の違い(経産省か厚労省)
【補助金の管轄省庁】
多くは経済産業省やその外局である中小企業庁です。その他、農林水産省、国土交通省、環境省など、事業分野に応じた省庁が管轄することもあります。
【助成金の管轄省庁】
主に厚生労働省です。雇用や労働条件に関する制度が中心となります。
公募期間の違い(期間限定か通年か)
【補助金の公募期間】
多くの場合、公募期間が限定されています。予算が決まっており、その予算枠に達し次第、または定められた期間で募集が終了します。人気の補助金は応募が殺到し、早期に締め切られることもあります。
【助成金の公募期間】
比較的通年で募集しているものが多い傾向にあります。ただし、年度の途中で内容が変更されたり、予算上限に達して早期終了したりする可能性もあるため、常に最新情報を確認することが重要です。
審査基準の違い(競争採択か要件充足)
【補助金の審査基準】
「競争採択」が一般的です。これは、申請された事業計画の内容を審査し、より優れたものや政策目標への貢献度が高いと判断されたものが採択される方式です。そのため、申請すれば必ずもらえるわけではなく、受給難易度は比較的高いと言えます。
【助成金の審査基準】
「要件充足型」が一般的です。これは、定められた支給要件をすべて満たしていれば、原則として受給できる方式です。そのため、補助金に比べると受給のハードルは低い傾向にあります。
補助金とは?目的・種類・注意点
次に、補助金について詳しく見ていきましょう。
補助金の定義と目的事業成長支援
補助金とは、国や地方公共団体が、政策目標を達成するために、事業者の行う事業経費の一部を支援するお金のことです。主な目的は、新規事業の創出、技術開発、設備投資、販路拡大など、企業の成長や社会課題の解決を後押しすることです。
補助金は、事業計画の実現性や将来性、政策への貢献度などが審査され、採択されると交付されます。
補助金の主な種類と対象経費
補助金には様々な種類があり、対象となる事業や経費も多岐にわたります。
代表的なものとしては以下のようなものがあります。
中小企業・小規模事業者等が行う革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資等を支援します。
対象経費例:機械装置費、技術導入費、専門家経費など。
中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)を導入する際の経費の一部を補助し、生産性向上を支援します。
対象経費例:ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費など。

小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援します。
対象経費例:広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費など。
中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
対象経費例:建物費、機械装置費、システム購入費など。
これらはあくまで一例であり、他にも地域限定の補助金や特定の産業向けの補助金など、数多くの種類が存在します。
補助金のメリット・デメリット
補助金を活用するメリットとデメリットを整理しておきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ①原則として返済が不要 融資とは異なり、返済の必要がないため、財務負担を軽減できます。 | ①競争率が高く、必ず採択されるとは限らない 魅力的な補助金ほど応募が集中し、採択されるのは一部です。 |
| ②事業拡大や新規事業への挑戦が可能になる 自己資金だけでは難しい大規模な投資や新しい取り組みに着手しやすくなります。 | ②申請手続きが複雑で時間がかかる 事業計画書の作成など、準備に手間と時間がかかることが多いです。 |
| ③金融機関からの信用力向上につながる場合がある 国の審査を通過した事業であるという点で、対外的な信用度が高まることがあります。 | ③原則として後払い(精算払い) 事業を実施し、経費を支払った後に補助金が交付されるため、一時的な資金繰りが必要になる場合があります。 |
補助金申請の注意点返済義務の確認
補助金は原則として返済不要ですが、注意すべき点があります。
それは、不正受給や補助金の目的外使用、その他交付条件に違反した場合には、補助金の返還を求められることがあるという点です。また、補助事業の実施後、一定期間は成果報告などが義務付けられることもあります。
申請前に公募要領をよく読み、ルールを正しく理解することが非常に重要です。
助成金とは?目的・種類・注意点
続いて、助成金について詳しく見ていきましょう。
助成金の定義と目的雇用安定支援
助成金とは、主に厚生労働省が管轄し、雇用の安定、職場環境の改善、従業員の能力開発などを目的として支給されるお金のことです。財源は主に雇用保険料であり、企業が労働関連の法令を遵守し、一定の要件を満たす取り組みを行った場合に支給されます。
企業の労働環境をより良くするための支援という側面が強いのが特徴です。
助成金の主な種類と対象経費
助成金も様々な種類があり、企業の状況や目的に応じて活用できます。代表的なものとしては以下のようなものがあります。
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ(正社員化、処遇改善など)を促進するため、助成措置を実施する事業主に対して助成します。
対象経費例:正社員化に伴う賃金増額分の一部、研修費用など。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成します。
対象経費例:休業手当、教育訓練費など。
労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
対象経費例:訓練経費、訓練期間中の賃金の一部など。
仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援します。育児休業の取得促進や、介護離職防止のための取り組みなどが対象となります。
対象経費例:育児休業取得者の代替要員確保費用、職場復帰支援費用など。
これらも一例であり、企業の規模や業種、取り組む内容によって様々な助成金が用意されています。
助成金のメリット・デメリット
助成金を活用するメリットとデメリットも確認しておきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ①原則として返済が不要 補助金と同様、返済の必要はありません。 | ①申請手続きや書類作成が煩雑な場合がある 計画書の提出や実施後の報告など、細かな手続きが求められることがあります。 |
| ②要件を満たせば受給できる可能性が高い 補助金のような競争採択ではなく、定められた要件を満たせば原則として支給されます。 | ②財源が雇用保険料のため、雇用保険の適用事業所であることが前提 雇用保険に加入していない個人事業主などは対象外となる場合があります。 |
| ③雇用の安定や労働環境の改善につながる 従業員のモチベーション向上や定着率アップ、企業のイメージアップにも貢献します。 | ③原則として後払い(精算払い) 取り組みを実施し、経費を支払った後に助成金が支給されるため、一時的な資金負担が発生します。 |
| ④通年で申請できるものが多い 企業のタイミングに合わせて計画的に申請しやすいです。 | ④法令遵守が厳しく求められる 労働基準法などの関連法規を遵守していることが大前提となります。 |
助成金申請の注意点手続きの煩雑さ
助成金は要件を満たせば受給しやすい一方で、申請手続きの煩雑さがデメリットとして挙げられることがあります。
例えば、事前に計画届を提出し、その計画通りに実施した上で、支給申請を行うという流れが一般的です。また、就業規則の整備や勤怠管理の適正化など、社内体制の整備が求められることも少なくありません。
申請書類の不備や期限の遅れは不受理の原因となるため、慎重な準備が必要です。
給付金・交付金との違いを比較
補助金や助成金と似た言葉に「給付金」や「交付金」があります。これらの違いも理解しておきましょう。
給付金とは?個人向け支援が中心
給付金とは、国や地方公共団体が、特定の条件に該当する個人や世帯、事業者に対して現金を支給する制度です。
補助金や助成金が特定の「事業」や「取り組み」に対する支援であるのに対し、給付金は生活困窮者支援や特定の政策目的(例:子育て支援、消費喚起など)のために直接的に金銭を給付するケースが多いのが特徴です。
例えば、新型コロナウイルス感染症対策として支給された持続化給付金(事業者向け)や特別定額給付金(個人向け)などがこれにあたります。
事業者向けの給付金もありますが、個人向けの支援というイメージが強いかもしれません。
交付金とは?国から地方への資金
交付金とは、国が地方公共団体(都道府県や市区町村)に対して、特定の行政サービスや事業を実施するために交付する資金のことです。
企業や個人が直接国に申請して受け取るものではなく、国から地方へ、そして地方から間接的に住民サービスや地域振興策として還元されるお金と考えると分かりやすいでしょう。
例えば、地方創生交付金などがこれにあたり、地方自治体がその資金を活用して独自の補助金制度を設けることもあります。
補助金・助成金・給付金比較一覧
ここまで見てきた補助金、助成金、そして給付金(事業者向けを想定)の主な違いを一覧表にまとめました。
| 比較項目 | 補助金 | 助成金 | 給付金(事業者向け) |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 事業成長支援 政策目標達成 | 雇用安定、能力開発 労働環境改善 | 緊急時の経済支援 特定の政策目的達成 |
| 主な財源 | 税金(法人税等) | 雇用保険 | 国の予算(税金等) |
| 主な管轄 | 経済産業省 中小企業庁など | 厚生労働省 | 経済産業省 中小企業庁 各省庁(内容による) |
| 公募期間 | 期間限定が多い | 通年募集が多い | 期間限定が多い (緊急時など) |
| 審査基準 | 競争採択 (事業計画で選定) | 要件充足型 (定められた要件を満たせば支給) | 要件充足型 (定められた要件を満たせば支給) |
| 受給難易度 | 比較的高い | 比較的低い | 比較的低い(要件による) |
| 対象経費 | 事業に必要な経費の一部 | 雇用関連、人材育成関連の経費の一部 | 使途が比較的自由な場合もある |
| 返済義務 | 原則なし | 原則なし | 原則なし |
この表はあくまで一般的な傾向であり、個別の制度によって詳細は異なります。
必ず各制度の公募要領などを確認してください。
自社に合う制度は?選び方のコツ
「結局、うちの会社はどの制度を使えばいいの…?」
そう思われる方もいらっしゃるでしょう。自社に合った制度を選ぶためのコツをいくつかご紹介します。
事業目的で選ぶ設備投資か雇用か
まずは、何のために資金調達をしたいのか、事業の目的を明確にしましょう。
【新しい機械を導入したい、新商品を開発したい、販路を拡大したいなど、事業そのものの成長や革新を目指す場合】
→ 補助金が適している可能性が高いです。
【従業員を新たに雇いたい、従業員のスキルアップを図りたい、働きやすい職場環境を整備したいなど、雇用や労働環境に関する課題を解決したい場合】
→ 助成金が適している可能性が高いです。
このように、事業の目的と各制度の趣旨を照らし合わせることが最初のステップです。
企業の状況に合わせて検討
次に、自社の状況を客観的に把握しましょう。
【企業の規模や業種】
制度によっては、対象となる企業の規模(中小企業限定など)や業種が定められている場合があります。
【財務状況】
補助金も助成金も原則後払いのため、一時的な資金繰りが可能か検討が必要です。
【抱えている課題】
人手不足、生産性の低迷、DX化の遅れなど、具体的な課題を洗い出し、それを解決できる制度を探します。
【申請準備にかけられるリソース】
補助金は事業計画書の作成など、準備に時間と労力がかかる場合があります。社内に対応できる人材がいるか、外部の専門家のサポートが必要かなども考慮しましょう。
自治体独自の制度も要チェック
国が実施する補助金・助成金だけでなく、都道府県や市区町村が独自に設けている支援制度も数多く存在します。
これらの制度は、国の制度よりも地域の実情に合っていたり、より小規模な事業でも利用しやすかったりする場合があります。
自社の事業所がある自治体のウェブサイトや窓口で情報を確認してみましょう。商工会議所や商工会なども情報源となります。
申請・受給の流れと情報収集方法
実際に補助金や助成金を活用するためには、どのような流れで進め、どこで情報を集めればよいのでしょうか。
補助金の一般的な申請ステップ
補助金の申請から受給までの一般的な流れは以下の通りです。ただし、制度によって詳細は異なります。
公募要領を確認し、自社が対象となるか、条件に合うかなどを確認します。
事業計画書、経費明細書など、必要な書類を作成します。必要に応じて認定支援機関などのサポートも検討しましょう。
指定された方法(電子申請が多い)で申請書類を提出します。
事務局による書類審査や、場合によっては面談審査が行われます。
審査を通過すると採択され、交付決定通知が届きます。
交付決定後、計画に沿って事業を開始します。**原則として交付決定前に着手した経費は対象外となることが多い**ため注意が必要です。
事業完了後、かかった経費の証拠書類とともに実績報告書を提出します。
提出された実績報告書に基づき、補助金の金額が最終的に確定します。
確定した金額が振り込まれます。
助成金の一般的な申請ステップ
助成金の申請から受給までの一般的な流れは以下の通りです。こちらも制度によって異なります。
支給要件を確認し、自社の取り組みが該当するか検討します。就業規則の整備などが必要な場合もあります。
制度によっては、取り組みを開始する前に計画届を管轄の労働局やハローワークに提出する必要があります。
計画に沿って、雇用、研修、制度導入などの取り組みを実施します。
取り組み完了後、定められた期間内に支給申請書と必要書類を提出します。
提出された書類に基づき、支給要件を満たしているか審査が行われます。
審査を通過すると支給が決定され、助成金が振り込まれます。
最新情報の入手先公的機関窓口
補助金や助成金の制度は、頻繁に内容が変更されたり、新しい制度が始まったりします。常に最新の情報を入手することが非常に重要です。
ミラサポplus(中小企業庁)
国や自治体の支援制度を検索できるポータルサイトです。

J-Net21(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
経営に関する様々な情報とともに、支援情報も提供しています。

各省庁のウェブサイト
経済産業省、中小企業庁、農林水産省など、関心のある分野の省庁のウェブサイトを確認しましょう。
各都道府県・市区町村のウェブサイト
地域独自の制度が掲載されています。
厚生労働省のウェブサイト
事業主の方への給付金(助成金)の情報がまとめられています。
都道府県労働局、ハローワーク
地域の窓口で相談したり、情報提供を受けたりすることができます。
専門家活用も視野に
「どの制度が使えるかわからない…」「申請書類の作成が難しそう…」
そんな時は、専門家のサポートを受けることも有効な手段です。
中小企業診断士
経営全般のコンサルティングを行う専門家で、事業計画の策定や補助金申請の支援を得意としています。
社会保険労務士
労働・社会保険に関する専門家で、助成金の申請代行や労務管理のアドバイスを行っています。
税理士・公認会計士
税務・会計の専門家で、資金調達に関するアドバイスや経費処理の相談ができます。
行政書士
官公署に提出する書類作成の専門家で、補助金・助成金の申請書類作成をサポートしています。
相談料や依頼費用はかかりますが、採択率の向上や手続きの負担軽減につながる可能性があります。
まとめ
今回は、補助金と助成金の違いを中心に、給付金との比較や選び方のコツ、申請の流れについて解説しました。
【補助金】は、主に経済産業省などが管轄し、事業の成長や革新を支援するもので、競争採択が一般的です。
【助成金】は、主に厚生労働省が管轄し、雇用の安定や労働環境の改善を支援するもので、要件を満たせば受給しやすい傾向にあります。
どちらの制度も、原則として返済不要という大きなメリットがありますが、申請には手間と時間がかかり、原則後払いである点などを理解しておく必要があります。
自社の事業目的や状況をしっかりと把握し、最新の情報を収集した上で、最適な制度を見つけて活用しましょう。
この記事が、皆様の事業発展の一助となれば幸いです。
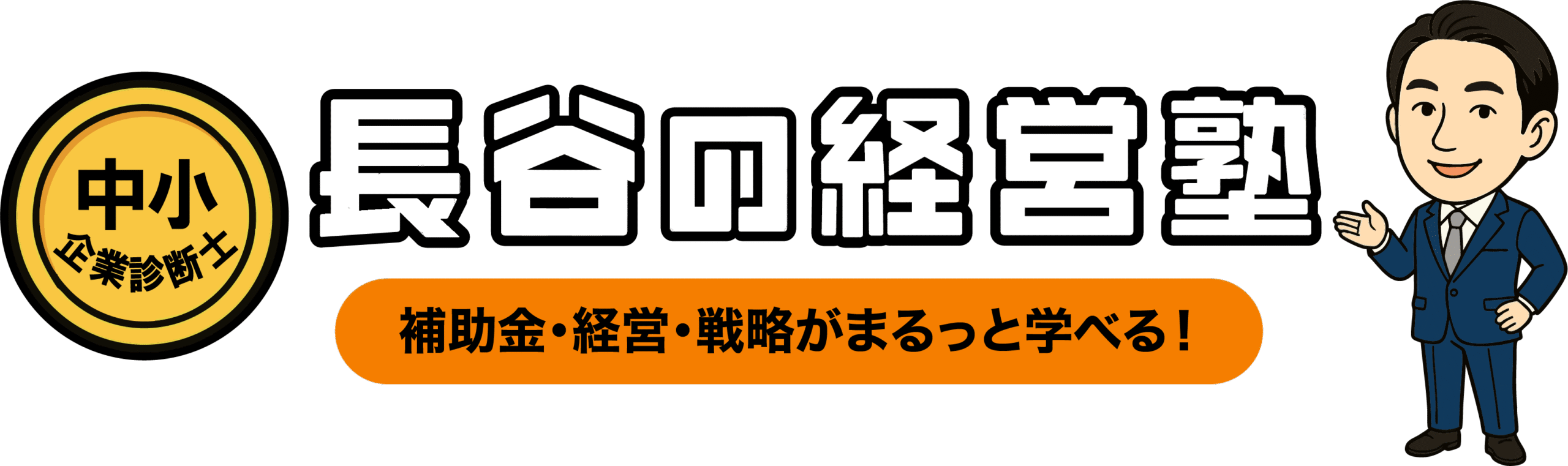

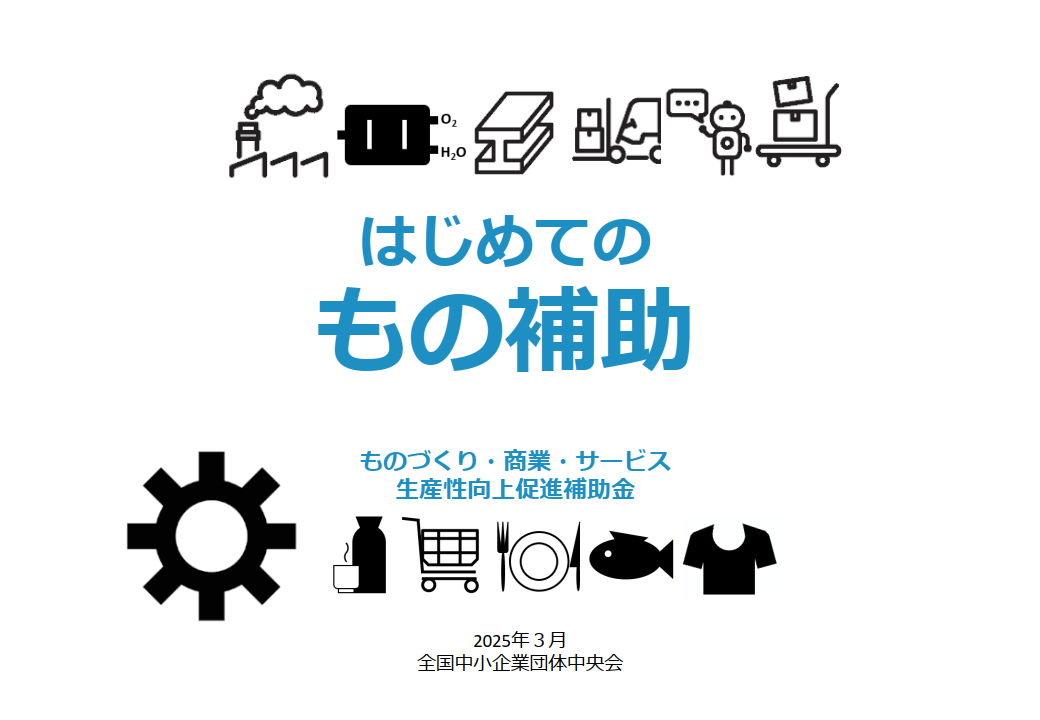
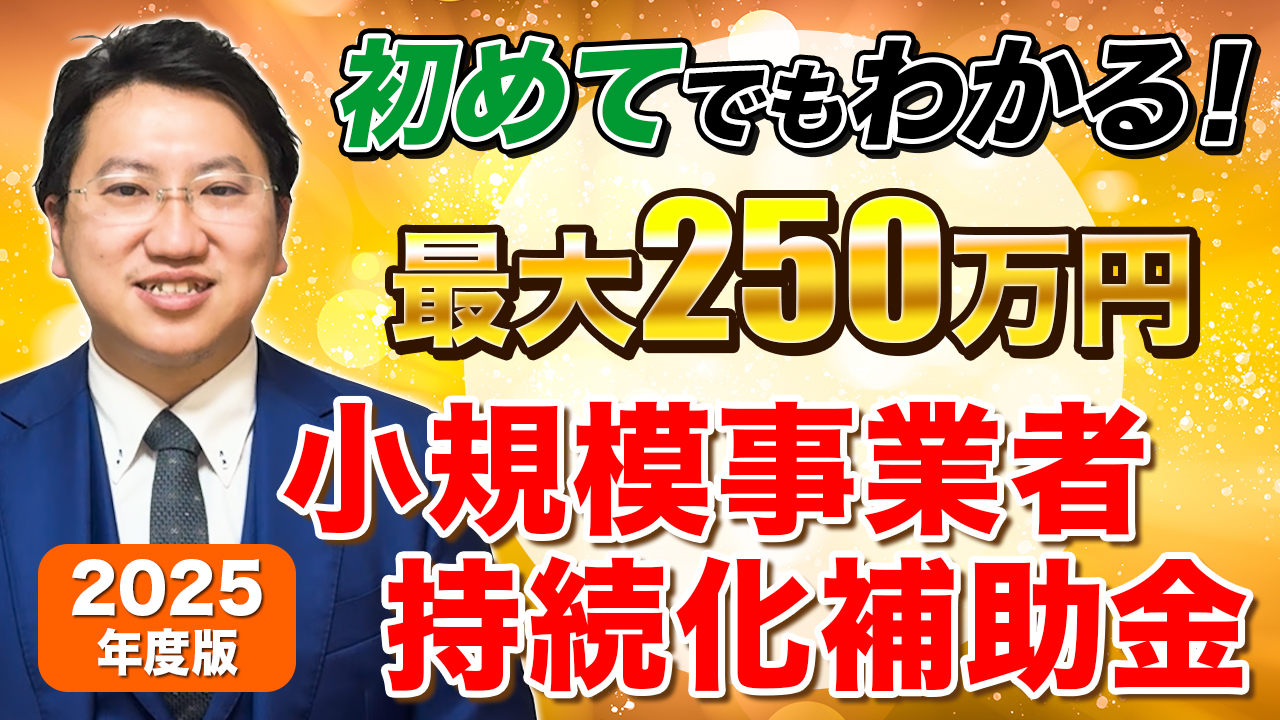
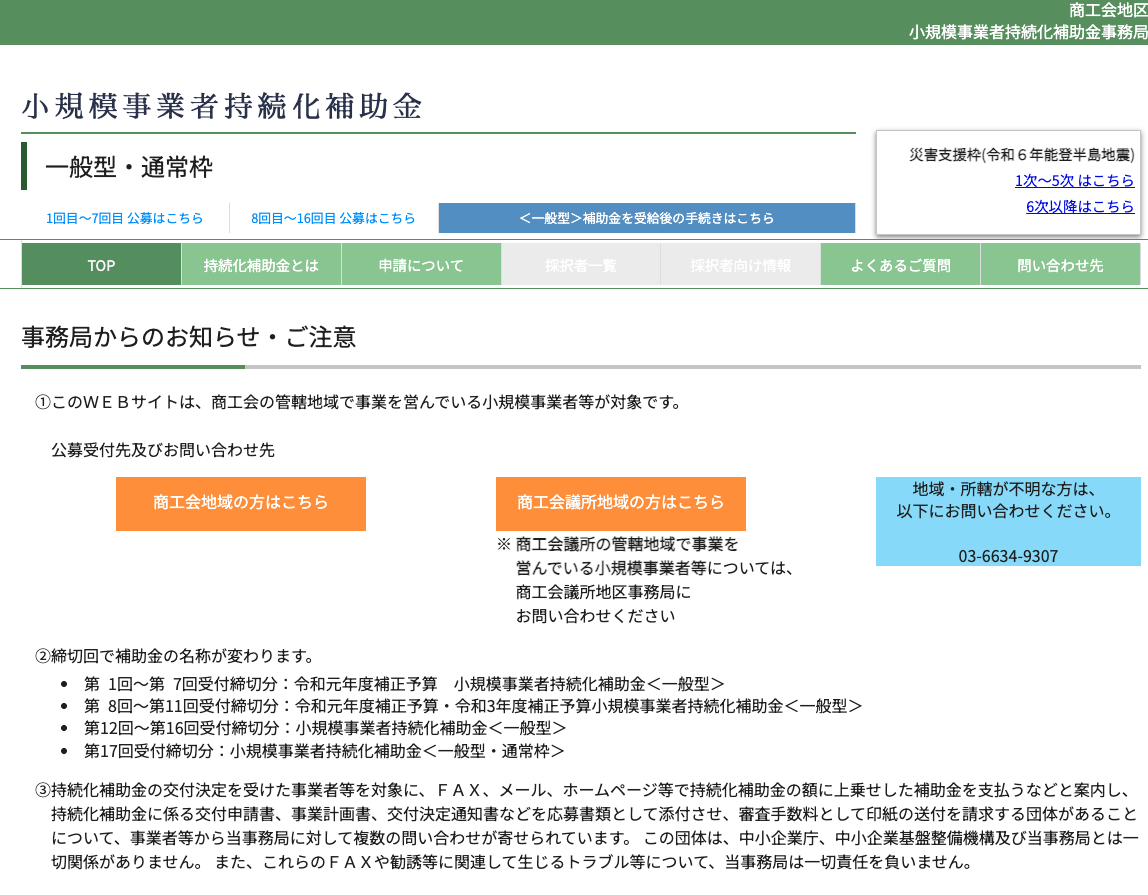








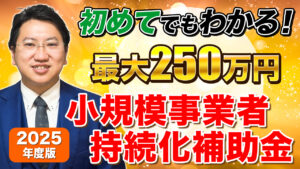
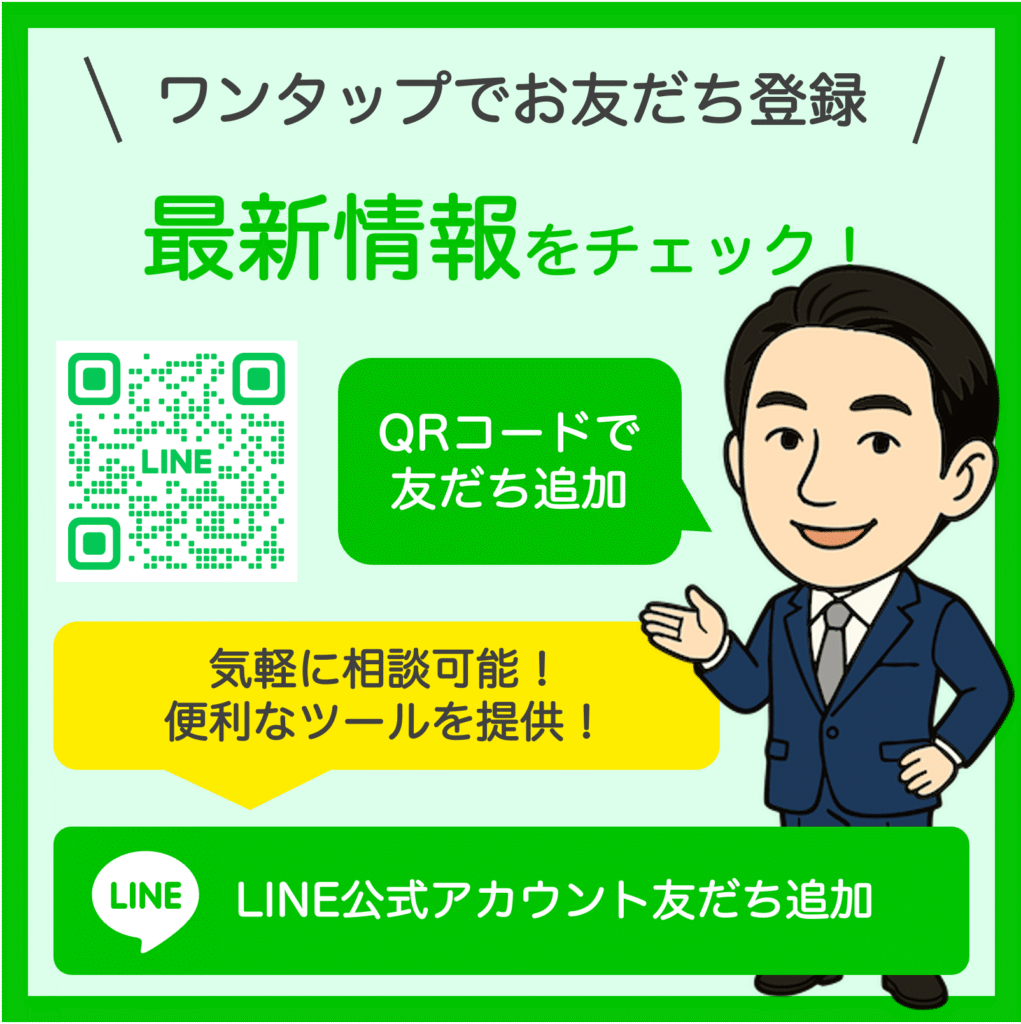
コメント